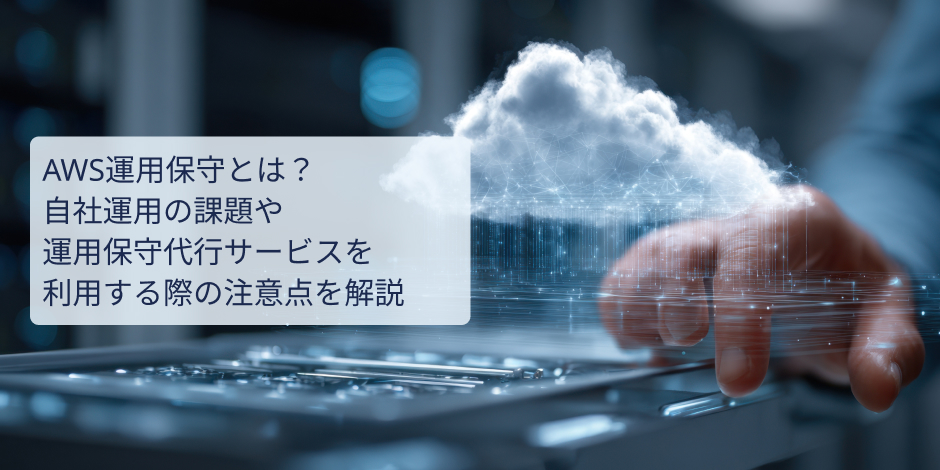
AWS運用保守とは?自社運用の課題や運用保守代行サービスを利用する際の注意点を解説
株式会社サイバーセキュリティクラウド
投稿日:2025/10/29
クラウド環境の活用が一般的となった現在、AWSを導入する企業が増え続けています。しかし、導入後の運用保守体制に課題を感じている企業が多いのも事実です。
社内に十分な知識やリソースがない状態でAWSを運用し続けると、障害対応の遅れ、セキュリティリスクの増大、予期せぬコスト増加といった問題が発生する可能性があります。こうした課題を解決する選択肢として、AWS運用保守代行サービスが注目されています。ただし、効果的な運用体制を構築するには、自社で担うべき領域と外部に委託すべき領域を適切に見極めることが重要です。
AWSの運用保守とは?重要性を解説
AWSの運用保守は、単にシステムを稼働させ続けることではありません。監視、バックアップ、セキュリティ管理、パッチ管理、障害対応など、多様な業務があります。ここでは、特に重要な3つの作業内容をご紹介します。
AWSの運用保守の主な作業内容3つ
AWSの運用保守では、主に「稼働状況の監視」「OSやアプリケーションの管理」「システムリソースの調整」の3つの業務が中心となります。
まず、稼働状況の監視とバックアップです。インスタンス(AWS上の仮想サーバー)やアプリケーションの動作を確認する「死活監視」、CPU負荷やメモリ使用率を監視する「リソース監視」などを行います。
次に、EC2インスタンス上のOSやミドルウェア、アプリケーションを最新の状態に保つことは、セキュリティとパフォーマンスの両面で重要です。パッチ適用は自動化もできますが、アプリケーションの互換性確認や適用タイミングの調整など、慎重な計画が必要です。特に、脆弱性が発見された際の緊急パッチ適用では、サービス影響を最小限に抑えながら迅速に対応する必要があります。
最後に、システムリソースの調整です。AWS環境では、CPUやメモリ、ストレージなどのリソースを状況に応じて柔軟に変更できます。リソース監視の状況により、アクセス増加時にはスケールアップやオートスケーリングを行い、逆に利用が少ない時間帯にはリソースを縮小することでコストを抑えることが可能です。たとえば、リザーブドインスタンスの導入やインスタンスタイプの変更、使用率の低いリソースの停止・統合などを通じて、パフォーマンスとコストの両立を実現します。
AWSの運用保守の重要性
「システムリソースの調整」で述べた通り、AWSは高い柔軟性と拡張性を提供しますが、「OSやアプリケーションの管理」で述べたように、ソフトウェアの管理はユーザに委ねられているため、パッチ適用など適切な運用なしにはそのメリットを活かせません。適切な運用は障害やセキュリティリスクを未然に防ぎ、サービス停止による業務への影響を最小化できます。バックアップや障害対策を徹底することで、万が一障害が発生した場合でも迅速な復旧が可能となります。
特に、企業の基幹システムや顧客向けサービスがAWS上で稼働している場合、その安定稼働はビジネスの信頼に直結します。運用保守は単なる「管理作業」ではなく、企業の信頼性と成長を支える中核的な役割を担っているのです。
AWSの運用保守を自社で行う場合の課題
AWSの運用保守を自社で対応する場合には、いくつかの壁に直面します。特に人材やナレッジの面での不足は運用の根幹を揺るがすため、運用保守を外部に委託する企業もあります。ここでは、自社運用における代表的な課題をご紹介します。
専門人材の確保が難しい
AWSの運用保守を担当するには、通常のインフラ知識の他にAWSやセキュリティに詳しい専門人材が必要になります。しかし、これらのスキルを兼ね備えた人材は市場でも希少です。また、採用や育成する場合でも相応のコストと時間がかかります。
経済産業省の試算によれば、日本国内では若年層の人口減少やIT人材の高齢化が相まって2030年までに約40万人から最大で80万人不足すると見込まれています。さらに、IT分野の中でもとりわけ深刻な人材不足が指摘されているのが、サイバーセキュリティ領域です。
国際的なセキュリティ資格認定団体であるISC2(International Information System Security Certification Consortium)が2024年に発表した調査によると、日本におけるセキュリティ人材の不足数は、2023年の約11万人から2024年には約17万人にまで拡大しています。わずか1年で6万人ものギャップが広がっている状況からも、その深刻さが伺えます。
AWS環境においても、セキュリティ設計やアクセス制御、ログ管理といった対応は高度な専門性が求められる領域であり、知識だけでなく実践的な対応力が重要です。社内でこうした人材を確保・育成することは、多くの企業にとって大きなハードルとなっています。
最新のナレッジや知識のキャッチアップが必要
AWSはサービスのアップデートが頻繁に行われており、新機能の追加や仕様変更が日常的に発生しています。そのため、運用保守を担当する人物は常に最新情報を学び続ける必要があります。
さらに近年では、技術の進化スピードがこれまで以上に加速しており、担当者個人の努力だけでは情報収集が追いつかないケースも増えています。特に、生成AI(Generative AI)の登場と普及によって、サイバー攻撃の手口もより巧妙化しています。
実際に、生成AIを悪用したフィッシングやマルウェアの自動生成といった新たな脅威が登場しており、それに対応するためには最新のセキュリティナレッジと対処力が必要です。しかし、多くの企業ではこうした情報のキャッチアップが追いついておらず、リスクに気づかないまま運用が継続されている状況も見受けられます。
AWS運用保守の現場では、こうした最新トレンドやセキュリティリスクに迅速に対応できる体制を整えておくことが不可欠です。そのためには、社内での学習と情報収集に加えて、外部の専門家やサービスとの連携も視野に入れることが重要だと言えます。
運用業務が煩雑で担当者の負担が大きい
AWSの運用保守では、日々発生する業務が前述の通り多岐にわたります。監視、アラート対応、バックアップの確認、リソースの最適化、セキュリティ設定の見直しなど、どれも継続的かつ確実な対応が求められるものばかりです。これらを少人数のチームや限られたリソースで回している企業では、担当者の負荷が非常に大きくなりがちです。
特に、監視業務は運用保守における中核的な業務の一つであり、インフラの稼働状況を24時間365日体制で監視する必要があります。常時対応の体制を維持することは、企業にとって大きな負担となります。万が一、障害が発生した際には、即時の原因調査や復旧対応に追われ、担当者が疲弊してしまうケースも少なくありません。
加えて、コストの管理も担当者にとって大きな課題となっています。AWSの多くのサービスは従量課金制を採用しており、データ量の増加や使用率の低いリソースの放置によって、想定以上の費用が発生することがあります。無駄なリソースを放置した結果、利用料金が高騰してしまうといった事例も少なくありません。
本来であれば、こうしたコストを抑えるために、システムのアーキテクチャやリソース構成を定期的に見直し、無駄のない構成に最適化していく必要があります。しかし、日々の保守対応に追われるなかで、コスト管理まで手が回らない企業も多く見られます。
このように、AWSの運用保守は業務の幅が広く、しかも常に最新かつ安定した対応が求められるため、担当者の負荷が増大しやすいという問題を抱えています。対応範囲が広がり続ける中、業務の一部を自動化したり、外部のサポートを活用したりすることで、持続可能な体制を整えることが求められます。
AWS運用保守代行サービスのデメリットにも注意
上記のような課題から、AWS運用保守代行サービスが活用されています。このサービスでは自社のリソース不足や知識不足を補うことができますが、すべてを外部に任せてしまうと当然ながらデメリットも出てきます。自社で実現したいことを見据えたサービス選びが大切です。
サービス内容は会社によって異なる
AWS運用保守代行サービスは、提供企業ごとに対応範囲やサービス品質に大きな差があります。特に障害発生時の対応体制は重要で、ビジネスへの影響を最小限に抑えるためには、迅速な復旧対応が欠かせません。多くのサービスは24時間365日の監視と即時対応に対応していますが、中には夜間や休日に対応できないケースもあるため、緊急時の体制をよく確認することが重要です。
また、監視や障害対応だけでなく、セキュリティパッチの適用やリソース管理まで一括で任せられるサービスもありますが、その分コストは高くなります。自社で対応可能な業務は内製し、高度な専門性が求められる部分のみを外部に委託するなど、必要に応じた使い分けが効果的です。
社内の人材育成が難しくなる
AWS運用保守を外部に委託すると、日常的な運用に関する知識やノウハウが社内に蓄積されにくくなるという課題があります。トラブル対応や構成変更などをすべて外部パートナーに任せることで、担当者は実践の機会を失ってしまいます。将来的に体制を見直したい場合や、内製化を進めたい場合に対応力が不足するリスクも生じます。
一方で、AWS運用のノウハウを丁寧に共有してくれる代行サービスも存在します。このようなパートナーを選べば、外部の専門知識を活かしつつ、社内へのノウハウ移転も可能です。人材育成とアウトソースのバランスを取ることで、持続可能な体制の構築につながります。
保守代行会社による影響を受ける可能性がある
AWS運用保守を外部に委託する場合、運用品質や対応スピードは委託先の能力に大きく依存することになります。たとえば、対応遅延や情報共有不足が発生すると、システム障害の復旧が遅れ、業務全体に影響が及ぶリスクもあります。また、外部に運用を任せるためには、自社のシステム構成や設計情報などの開示が必要となります。たとえNDAを締結していたとしても、情報漏えいのリスクを完全に排除することはできません。
このようなリスクを最小限に抑えるには、セキュリティの認証を取得していたり、実績豊富なAWSパートナー企業を選定することが重要です。AWS認定のスキルバッジの有無や、APN(AWSパートナーネットワーク)への登録状況、さらにMSSPコンピテンシーを取得しているかどうかも、信頼性を見極める指標となります。MSSPコンピテンシーは、AWSがフルマネージドのセキュリティ運用(24時間365日の監視、脆弱性管理、MDR、WAF運用など)を所定の基準で提供できることを検証したパートナーに与えられる認定であり、実運用能力の裏付けになるでしょう。
セキュリティはAWS運用保守の中でも特に専門性が高い
前述の通り、AWSの運用保守と一口に言っても、その範囲は非常に広いことをご理解いただけたと思います。企業によっては、特定業務だけを内製し、残りを外注するハイブリッド型の体制を取るケースも少なくありません。
なかでもセキュリティ運用は、他の保守業務と比べて専門性が必要であり、対応の難易度が上がります。サイバー攻撃の手法は日々進化しており、脆弱性情報も常に更新され続けています。そのため、単なる監視やパッチ適用だけでなく、最新の脅威に基づいた運用体制の継続的な見直しと改善が必要です。
こうした背景から、セキュリティ運用を内製で担うのは負担が大きく、限られた人材や予算では十分な対応が難しく、外注する企業も多くなっています。セキュリティ領域は、専門性の高さゆえに外部ベンダーとの連携が必要となります。
AWSセキュリティの運用なら「CloudFastener」
こうしたセキュリティ運用の課題に対応すべく生まれたサービスが、CloudFastener(クラウドファスナー)です。CloudFastenerは、AWS環境のセキュリティに特化したMSS(マネージド・セキュリティ・サービス)+αのサービスです。一般的なMSSでは対応が難しい領域までをカバーし、お客様ごとに最適化されたコンサルティングと、運用負荷を最小限に抑える設計を提供しています。
CloudFastenerでは、セキュリティ専門家がクラウド環境を分析してリスクを特定し、最適な防御策を設計することで堅牢な体制を実現します。24時間365日の監視により、セキュリティアラートに対する適切な処置とサポートを提供します。また、ID・権限管理や脅威の可視化を通じて、内製チームのような柔軟性とスピード感でお客様のクラウド環境を守ります。加えて、専門家がオンライン常駐して伴走し、日々の運用や改善案を提供し、ナレッジが定着するよう支援します。
CloudFastenerは日本企業として初めて、世界でも14社目としてAWSレベル1 MSSPコンピテンシーパートナーに認定されています。さらに、AWSファンデーショナルテクニカルレビュー(FTR)の認証も取得しており、高い信頼性と実行力を備えたサービスです。
AWS環境のセキュリティ対策を本格的に検討されている企業様は、ぜひCloudFastenerのサービス内容をご確認ください。
サービス資料のダウンロードはこちら





